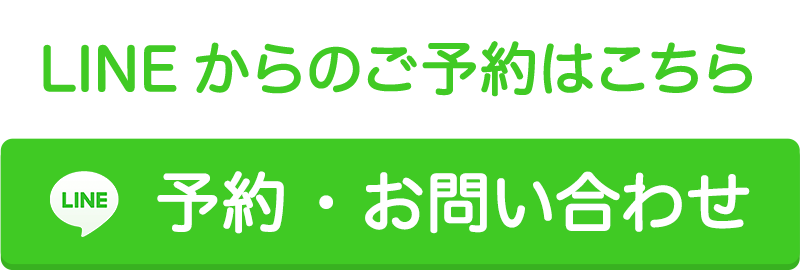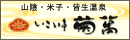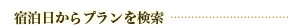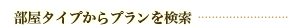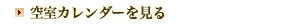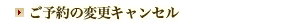山陰・米子・皆生温泉 政府登録国際観光旅館 海辺の宿 皆生 菊乃家
日本海の海を庭園に見立てた心やさしき海辺の宿

トップ > 松葉かに(松葉ガニ・松葉蟹)の美味しい食べ方
松葉かに(松葉ガニ・松葉蟹)の美味しい食べ方
塩など一切の調味料は使用しませんので、カニ本来のカニ味噌が味わえます。
濃厚なカニのほろ甘い味に舌づつみした後は、お好みで甲羅酒にしてはいかがでしょう。
カニ刺しは、鮮度が一番で、活でなくてはなりません。身をカラからはずし、5分後冷水に漬けておくと、白い花のように、花ひらきます。
野菜も、地元大山ほか近辺で作られた物を使用、さながら地産地消を地で行く一品に仕上げております。
カニの殻から出るエキスと冬野菜の甘みが溶け合うダシは絶妙の味です。カニの身は、レアなうちに味わう方が本来の旨みがよくわかります。
ちり鍋・すき鍋は、殻の色が変わったら引き上げて、火を通しすぎず、身がふわっとした状態が食べ時です。
米は、地元農家さんが丹精こめて作っていただいたものを使用、卵もまた地元産で卵黄のしっかりした味の良いものを使用しております。
出汁を多くして雑炊、少なくしておじや、お好みで作って最後までカニを堪能しましょう。
「カニシーズンを迎え、期待以上のお料理で大変美味しく頂きました。料理長さんにお礼申し上げます。」(兵庫県70代N様)
「夕食は特に新鮮な松葉蟹のお刺身に感動しました!」(愛媛県50代T様)
「かに大満足です!刺身ももっと食べたかったです・・・。焼き・お鍋・茹で・すべて美味しかったです。」(大阪府60代S様)
「質量ともに大満足です。いい親孝行ができました。また利用したいです。」(岡山県40代H様)
「あちこち旅行に行っていますが、皆生温泉でカニを食べたのは初めてでした。こちらのカニのおいしさに驚きました!」(福岡県60代I様)
山陰地方では、成長したズワイガニのことを松葉がにと呼びます。自然豊かな山々から滋養豊富な恵みが注がれた日本海で育った松葉がには、上品な旨みが楽しめる代表的な冬の味覚です。
毎年11月に解禁になると、鳥取沖や境港沖を中心にカニ漁でにぎわいます。生きたまま持ち帰られるのは、山陰と越前だけだといわれ、水揚げされた松葉がには鳥取の冬の風物詩となっています。
「松葉がに」とは、成長したズワイガニの雄で山陰地方の名称です。北陸地方では「越前がに」と呼びます。「松葉がに」という呼び名が雌雄を含めた総称として使われることもありますが、正確には成長しきった雄を「松葉がに」、雌を「親がに」または「子持ちがに」、脱皮して間もない雄を「若松葉がに」と呼んで区別します。
 |
 |
松葉がには殻が固く、ずっしり重くてハサミが太いものです。若松葉がには脱皮後間もないので、殻が柔らかいのが特徴です。値段が松葉がにと比べて安いので、地元では隠れた人気者です。また、親がにはお腹のフタが丸く、卵を抱えています。外から見えるのが「そとこ」と呼ばれる卵巣です。親がにの味噌汁は鳥取では家庭料理として馴染み深い料理です。かにすき、かに刺、焼きがに、かに味噌など、松葉がにの地元・鳥取でかに三昧をぜひご堪能ください。
 |
 |
「松葉がに」の名前の由来は、諸説あります。細長い脚の形や脚の肉が松葉のように見えるという説、かにの脚の殻をはいで、水につけると松葉のように広がるからとか、漁師が浜で大鍋を据え松葉を集めて燃やしたからなどなど、いずれも定かではないようです。松葉がにの名称が登場する最古の文献は、弘化2年(1845年)に書かれた鳥取藩の「町目付日記」になります。そこでは、11月3日の項に屋敷建て替えの際、棟上げ祝宴に出された献立の一つに「松葉がに」が記されていました。それにちなんで、鳥取県では11月の第4土曜日を「松葉がにの日」としています。
タグ付きガニは、県により違うのですが、鳥取県の場合白地に赤字で松葉ガニ、船名が記されています。 水揚げが多いので500g以下の物はタグが付いてない物もあります。

1.日本有数の水揚げ量を誇る境港からすぐ近くの立地
皆生温泉は松葉蟹が水揚げされる境港から一番近い温泉地です。
実は境港は、安価に楽しめる紅ズワイガニの水揚げ量日本一。そして、境港沖合から隠岐にかけては松葉ガニの好漁場なのです。水揚げされたばかりの松葉ガニは、すぐ横の市場で即セリにかけられ、新鮮なまま旅館へ届けられます。
2.館内に「生け簀(いけす)」があるからより新鮮な状態のまま!
皆生菊乃家は、館内に生簀をもうけ700gから1kgまでの活きの良いタグ付きの松葉ガニを生かしております。お客様のご予約の時間に合わせて料理しますので、活きの良い松葉ガニを鮮度良くお召し上がり頂くことができます。
3.料理長荒田とそれを支える最高のパートナーの選球眼
当館の松葉蟹を語る上で欠かせないのが皆生温泉で唯一当館とのみ取引をしている仲買人の存在です。料理長荒田が、約20年間にわたって信頼関係を築いているこの仲買人(パートナー)と、境港の入船状況を把握しながら綿密に打ち合わせを行いその時期で最良の質の蟹を仕入れるよう力を入れております。